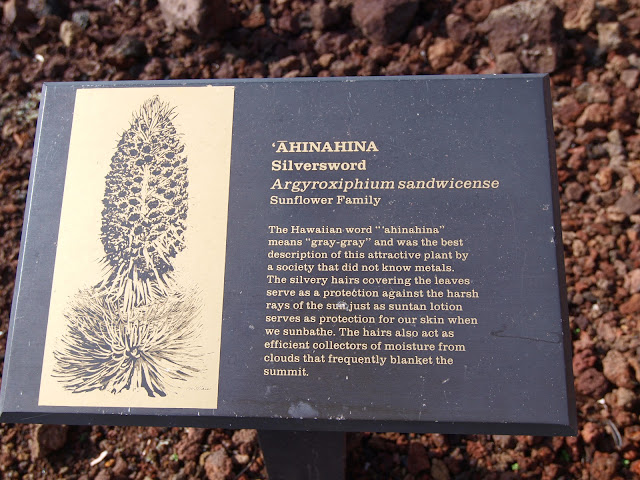忌わしい記憶ゆえ、どうやら無意識にブログに掲載するのをやめていたようだ。
最近になって「あれ?あのダイブの記述はブログに掲載していないぞ」と気づいたのだ。
それが、プラヤ・デル・カルメンという街のビーチから100mくらい沖のポイントで潜ったBull Shark ダイブ。
ブルシャークは、日本語でオオメジロザメというらしい。
セノーテダイビングでお世話になっていたショップのマリーナさんが
「今のシーズンは妊娠したブルシャークがプラヤの海に集まる絶好のシャークシーズンよぉ!」と興奮気味に
言うもんだから、まるきちたちも行ってみることにした。今、Wikiで見ると、すごくアグレッシブな怖い鮫さんらしい・・・(汗)
どこのダイブショップでもブルシャークツアーをやっているし、ツアーに申し込んだときは怖いとは思わなかった。
・・・しかし、このダイビングはまるきちの心身に思いがけない傷跡を残すのであった・・・
車でTulumからプラヤまで約1時間。同じくブルシャークダイブに申し込んだスペイン人カップルと
おしゃべりしながら、あっという間に着く。
このカップル、旦那は脱サラしてインターネットで太陽光パネルを売る仕事をしているらしい。
「ネット販売だから、どこにいても仕事ができる」と言われても、「ん?仲介するだけ?」と
イマイチ肝心の金の稼ぎ方が分からない。
まぁ、何はともあれプラヤに到着。
え?思ったよりもプラヤ・デル・カルメンのど真ん中。
ものすごい数の観光客やジモティーがビーチで思い思いに遊んでいる。
そこから船に乗るらしい。
「すぐ近くだから、もうウェットスーツも着てしまって。」と指示され、ますます困惑。
ブルシャークが10匹単位でいるという海域は、子供が遊びまわっているようなビーチの近くでは
ないはずと
思い込んでいたのだが、ダイブポイントはビーチで泳ぐ人たちが肉眼で確認できる程度の沖であった。
少々ショックを受けつつ、潜る準備をする。まるきちたちの先に潜っている一団がいるようだ、
ダイバーが戻ってくるのを待っているボートがいる。
マリーナさんに「必ず一緒にいること、離れてはいけない。砂場に足を落ちつけていたら
だいたいは向こうから近寄ってくる」ということで、その指示通りに
一気に潜航して、何も無い、魚もほとんどいない綺麗な砂地へドシーン。
砂地で待つこと1分、2分。
砂地で待つこと1分、2分。
まず、まるきちたちの姿をチェックアウトしに来たのはコイツ。Remora、コバンザメ君である。
大きな鮫に付着して泳いでいる姿は見るが、単独で動き回っているやつは珍しいので
ちょっと嬉しかった。付着するために頭が平らでおかしな容姿。目つきは悪いが、受け口なのはご愛嬌。
そうこうしていたら、やってきた、でっかいブルシャーク。
パラオで頻繁に見たグレイリーフシャークとかと違って、ずんぐりとして丸々太っている。
太っているのは妊娠しているからとも言えるが。
このダイブ、残念ながら、かんきちのカメラワークがイマイチで、フラッシュに反射した
砂塵が邪魔してすかっとした写真が少ない。お許しあれ。
合計10匹もいたかなぁ。6匹くらいはいた。ダイブ自体は大満足。ずんぐり丸々した鮫が
悠々と白い海底を泳ぎ回る姿は優雅で、迫力もあった。
すぐ近くで見られたのも嬉しかった。
割と全方向にいたので、たまに頭上を見上げると
「え?狙ってる?」的にこちらに向かってくる鮫なんかがいて、仰天する。
しかし、まるきちを襲った惨事について、ここで書かねばならない。
鮫がちらほら出始めて、「おお!」と盛り上がってきたまるきちのオデコに、軽い痛みが走った。
「ん?」と最初は理解ができなかったのだが、次には同じくオデコに激痛が!
「うわー!」と海中にも関わらず叫び声を上げるまるきち。
ゴボゴボッ。ゲホッ。水を飲んじまってむせるまるきち。
原因はコイツ。
体長20-30cmほどのモンガラである。地味な魚だが、歯が鋭い。
アジア海域では頻繁に見かけるゴマモンガラ(※)のような恐ろしい顔をしていたら気付いただろうが
こいつは地味で普通の顔つきであったため、その歯が目に入っていなかった。
今見ると、悪人相(魚相)じゃないか、こいつ。
※ゴマモンガラは、大きくて顎が非常に強いので、手をやられると、指ごと持っていかれる可能性あり。
こいつは縄張り意識が強く、特に卵をうみつけた巣の周辺なんかに入ってしまうと
追い出しにかかるのである。
ダイバーを追い出し慣れているとしか言いようがない。
顔の中で割と皮膚が丸出しになっているデコを狙ってくるとは・・・痛かった。
しかし、まるきちがパニックしたのは、痛かったからだけではない。
手袋の先にちょっと血がついたのだ。
「え?ブルシャークに囲まれているこの状況で血が・・・?!
何してくれんねん、この魚!」とキレ気味。
出血を抑えようと、デコを片手で押さえつつ、忌々しげにモンガラをにらみつけ、
ちょっと体の位置をずらしてモンガラの攻撃を防ぐ。
そんなまるきちの様子を隣で見て喜んでいたのはかんきち。
まるきちとモンガラの攻防戦の様子をカメラに収めていた。
左、まるきち。モンガラが2匹がかりでまるきちを攻める。隣2人がスペイン人カップル。
また、デコをおさえつつ、ブルシャークの動きに視線をキョロキョロさせるまるきちの
様子を写真に収めて喜んでいたようだ。
ホテルに戻ってから撮影したまるきちのデコ。
モンガラの上下2本ずつの歯型がうっすら残っている。
軽傷なのに、大の大人がパニクっちまった。コンチクショーメ。
ええ、分かっているんですよ、お魚さんの領域に無断で入ったのはこっちだってのは。
でもね、くやしいもんはくやしいんです。